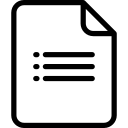企業価値評価とは?
M&Aにおける企業価値評価とは、企業全体の経済的価値を数値化し、売り手と買い手が納得できる価格交渉の土台を築く重要なプロセスです。主なアプローチとして「コストアプローチ(時価純資産法など)」「マーケットアプローチ(マルチプル法など)」「インカムアプローチ(DCF法など)」の3種類があり、それぞれ特徴とメリット・デメリットを踏まえて選択・併用するのが一般的です。算定手法には、貸借対照表を基に企業の純資産を評価する時価純資産法、業界標準の倍率を用いるマルチプル法(EBITDAマルチプル等)、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くDCF法などがあり、ケースに応じて最適な方法を組み合わせます。本記事では、定義から各アプローチの比較、具体的な計算方法までを整理し、企業価値評価の全体像をわかりやすく解説します。
企業価値評価とは?
定義と目的
定義と目的
企業価値評価とは、M&Aの交渉基準となる企業全体の価値を算定するプロセスを指します。ここでいう「企業価値」には、有形固定資産や運転資本などの事業資産に加え、のれんや営業権などの無形資産、さらには非事業資産も含まれます。特に非上場企業では市場価格が存在しないため、専門家による客観的かつ論理的な評価が不可欠です。また、企業価値の中でも「株式価値」を求めることが売り手の譲渡価格、買い手の提示価格を決定するうえで最も重要な指標となります。
企業価値評価には大きく以下の3つのアプローチがあります。
● コストアプローチ
- 概要:貸借対照表上の純資産を時価に置き換えて評価する手法。
- 代表例:主に「時価純資産法」などがあり、土地や建物など有形資産の含み益・含み損を反映し、営業権(のれん)を加味して算定します。
● マーケットアプローチ
- 概要:同業他社や類似取引の市場価格をベンチマークとし、倍率(マルチプル)を乗じて評価する手法。
- 代表例:EV/EBITDA倍率法、PER倍率法などがあり、業界動向や上場企業の事例を参考にします。
● インカムアプローチ
- 概要:将来予想キャッシュ・フロー(FCF)を適切な割引率(WACCなど)で現在価値に割り引いて評価する手法。
- 代表例:DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)で、複数シナリオを想定して感度分析を行うことも一般的です。
アプローチ別のメリットとデメリット
| アプローチ | メリット | デメリット |
| コスト |
|
|
| マーケット |
|
|
| インカム |
|
|
企業価値の算定方法
● 時価純資産法(コストアプローチ)
● マルチプル法(マーケットアプローチ)
● DCF法(インカムアプローチ)
- : 年目のフリー・キャッシュ・フロー(Free Cash Flow)
- :加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital)
- :明示的予測期間(通常は5〜10年)
- :ターミナルバリュー(継続価値、 年目以降の企業価値)
将来のキャッシュ・フロー予測が評価精度の鍵となります。
まとめ
M&Aにおける企業価値評価は、売り手と買い手双方が合理的・客観的に価格を導き出すための要となるプロセスです。主に「コスト」「マーケット」「インカム」の3つのアプローチがあり、それぞれの手法には得意領域と限界があります。実務では複数の手法を併用し、感度分析やシナリオ分析を行うことで評価精度を高めるのが一般的です。適切な評価を行うことで、M&A交渉をスムーズに進め、企業の将来価値を最大化する一助となります。今後M&Aを検討する際は、各手法の特徴と自社の事業ステージを踏まえ、最適な評価アプローチを選択してください。